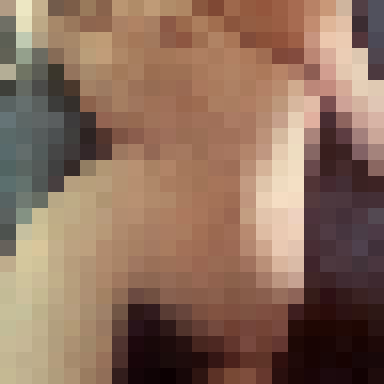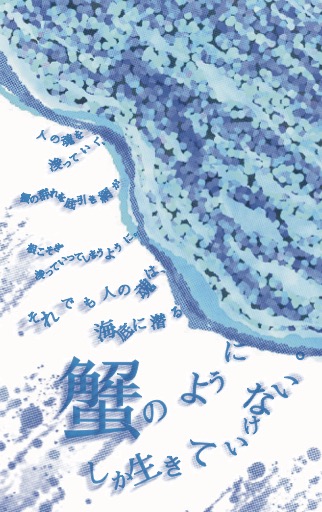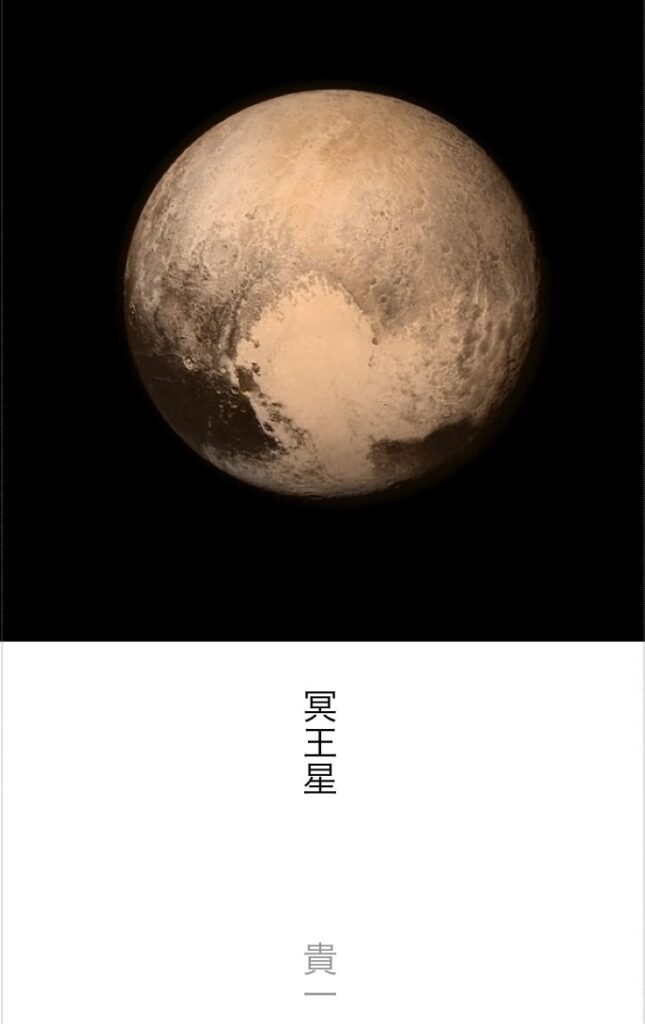35年前、はじめてこの聖堂を訪れたとき、外壁には落書きが残り、工事はどこか混沌としていた。巨大な未完の建築。観光地というより、終わらない実験場。あれが完成する日が来るのか――正直、信じきれなかった。
20年前に再訪すると、塔は確実に伸び、ファサードは姿を現していた。それでもまだ半分ほど。クレーンは林立し、「永遠の未完」という言葉が似合っていた。
そして現在、ほぼ完成に近づいた姿を前にすると、胸が熱くなる。遂に、ガウディの夢が叶おうとしている。
だがここで問いたいのは、「この聖堂は誰が建てているのか」ということだ。
設計者である アントニ・ガウディ の天才性ばかりが語られる。しかし実際に140年以上にわたる建設を支えてきたのは、国家でも王室でもない。
答えは、私たちである。
サグラダ・ファミリアは「贖罪聖堂(Expiatory Temple)」として始まった。つまり、信徒の献金によって建てる教会。スペイン政府の国家予算は投入されていない。ローマ教皇庁からの直接的な財政支援も基本的にはない。宗教的には2010年に ベネディクト16世 によって小バシリカに認定されたが、財務的には独立している。
最大の資金源は、観光客の入場料だ。
年間数百万人が訪れ、そのチケット収入が工事費に充てられる。パンデミックで観光が止まったとき、工事も縮小せざるを得なかった。つまりこの建築は、観光の動向と直結している。信仰と観光資本が融合した、極めて現代的な聖堂なのである。
加えて、世界中からの寄付、オフィシャルグッズ販売、出版物、ライセンス収入も循環している。もはやこれは単なる教会ではなく、文化ブランドであり、巨大なエコシステムだ。
35年前、落書きだらけだった外壁を思い出す。あの頃は、未完の象徴だった。20年前は、進行中の巨大プロジェクト。そして今は、完成目前の世界遺産。
だが視点を変えれば、これは一人の建築家の夢の達成というより、無数の無名の人々の小さな支払いの累積だ。
チケットを買った人。寄付をした人。模型を購入した人。彼らの数十ユーロが石に変わり、塔に変わり、光の柱になっていく。
国家の威信ではない。帝国の権力でもない。
市民の参加によって育った聖堂。
だからこそ、完成に近づく今、私は単なる観光客の感動以上のものを感じる。自分もまた、チケットを買った一人として、この建築の時間に参加しているのだという実感。
遂にガウディの夢が叶おうとしている。
しかしそれは同時に、140年にわたり世界中の人々が支え続けた夢の結晶でもある。
サグラダ・ファミリアは、石でできた建物でありながら、実は「支払いの連なり」でできている。
祈りと資本。信仰と観光。
その交差点に立つこの聖堂は、現代における最も純粋な公共建築のひとつなのかもしれない。